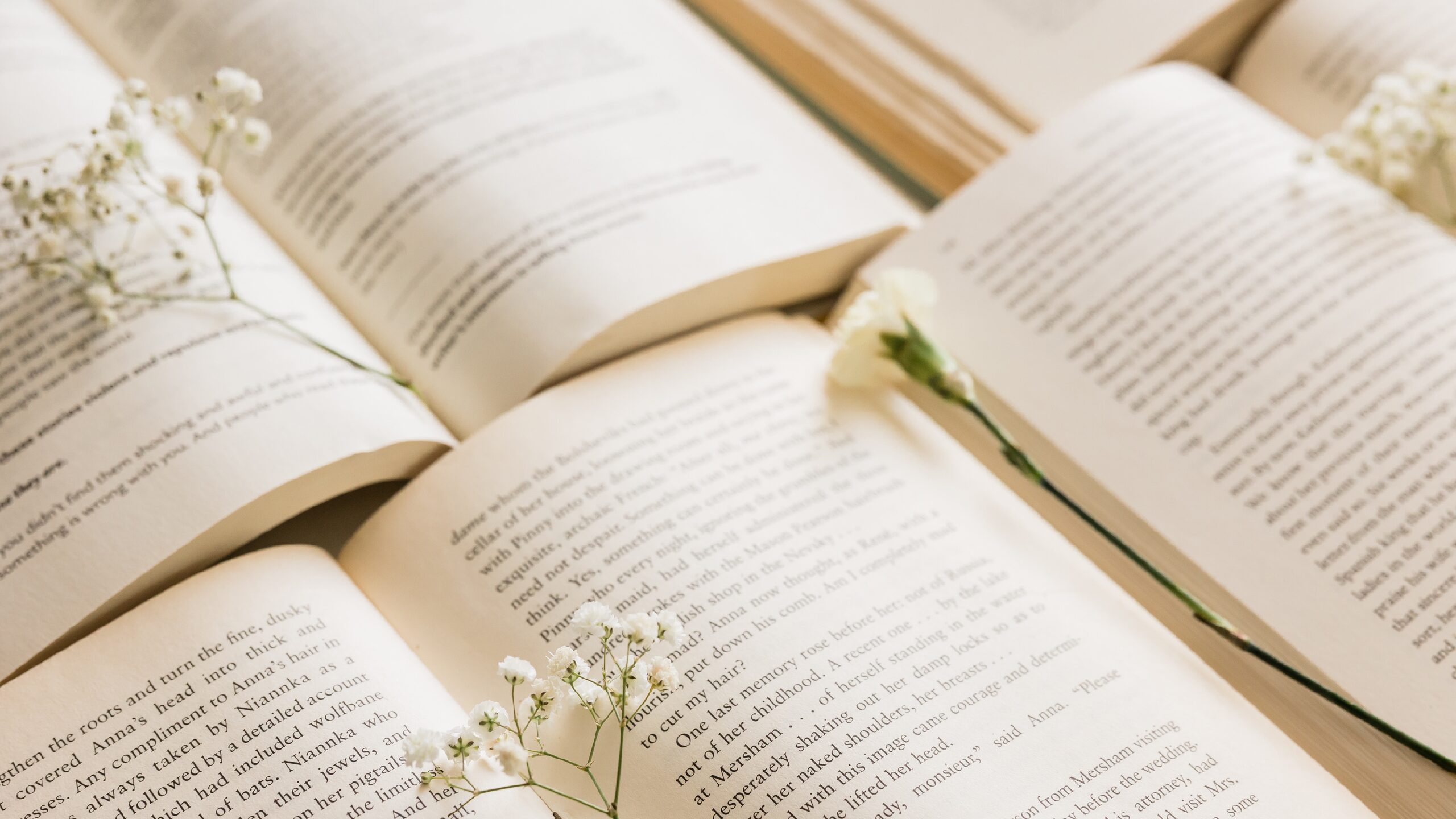成年後見制度で実際に起きたトラブル事例と回避のポイント
成年後見制度は、高齢者や判断能力が低下した方の生活を守るために作られた大切な仕組みです。
しかし、実際の運用では後見人とのトラブルや家族間の対立など、思わぬ問題が起こることもあります。
この記事では、成年後見制度のトラブル事例をもとに、注意すべきポイントと事前の備え方をわかりやすく解説します。
トラブル事例① 後見人による財産の不正管理
家庭裁判所が選任した後見人が、本人の財産を私的に流用してしまうケースがあります。
たとえば、本人名義の預金から無断で引き出したり、家族名義の口座に移したりするなど、金銭トラブルが発生することも。
【回避のポイント】
- 家庭裁判所への定期報告をしっかり確認する
- 後見人にすべてを任せきりにせず、家族も状況を把握しておく
- 信頼できる専門職(行政書士・司法書士など)を後見人候補に選ぶ
トラブル事例② 家族間の意見の対立
後見人の選任をめぐって、家族同士が「誰がやるか」で揉めるケースがあります。
また、後見開始後に「お金の使い方」や「施設入居の判断」を巡って、家族間で不信感が生まれることも。
【回避のポイント】
- 元気なうちに「任意後見契約」で信頼できる人を指定しておく
- 家族で話し合い、意思を共有しておく
- 第三者の専門家を交えた契約で、感情的な対立を防ぐ
トラブル事例③ 本人の希望が反映されない
後見人が法律上の「利益」を優先するあまり、本人の希望が叶えられないケースもあります。
「旅行に行きたい」「孫に少しお小遣いを渡したい」といった本人の思いが、法律的に“無駄遣い”と判断されることも。
【回避のポイント】
- 判断能力があるうちに、本人の希望を「任意後見契約書」に明記しておく
- 日常生活の希望や価値観を、見守り契約などで記録しておく
- 後見人に「本人の想い」を共有しておくことが大切
トラブルを防ぐためにできること
成年後見制度は非常に有用ですが、制度を利用する前の準備と設計が重要です。
信頼できる第三者に相談しながら、「誰に何を任せたいか」を明確にしておくことで、後のトラブルを防ぐことができます。
とくにおひとり様や、家族が遠方にいる方は、見守り契約や任意後見契約を組み合わせることで、より安心した生活設計が可能です。
まとめ
成年後見制度は、支援を受ける人を守るための制度ですが、運用を誤るとトラブルにつながることもあります。
制度の仕組みを正しく理解し、信頼できる人や専門家と契約をしておくことが、安心につながります。
新潟市で成年後見制度や見守り契約のご相談をするなら、かなで行政書士事務所へ。
トラブルを避けるためには、信頼に基づく関係づくりが欠かせません。業務的ではなく、家族のように支え合える関係をご所望の方に寄り添います。
あなたの大切な想いと財産を守るために、最適なサポートプランをご提案いたします。